こんにちは!
幅広い制作領域を武器に「新たな驚きと感動を作る」制作会社ジーアングル ブログ編集部です。
多くのゲームにとってグラフィックやサウンドと同じく、ゲームのクオリティを左右する大切な要素である「音声」。
そんな音声の収録現場で現場進行や声優さんの演技アシスト、時には台本監修までを担うのがジーアングルにおける「演出」です。
今回はそんな音声収録における演出について、ジーアングルの演出、佐藤滉世へインタビューを実施!
ゲーム音声収録特有の課題を解決し、ゲームの魅力を最大限引き出す「演出」の役割やメリットについて聞きました。ぜひ最後までご覧ください。
ゲームの音声収録における「演出」とは?
──本日はよろしくお願いします!
よろしくお願いします!
──早速ですが、グラフィックやサウンド同様、音声もゲームのクオリティやユーザー満足度をアップさせる大切な要素ですよね。そんなゲーム音声制作において、演出はどんな役割を担っているのでしょうか?
演出は音声という側面から、クライアントさんが思い描くイメージに一番近い世界観を創り上げる役割だと考えています。
ディレクターや、監修する範囲はアニメと少し異なりますが音響監督と呼ばれることもありますね。
──音声面から世界観を作り上げる…具体的にはどんなことをされているのか伺いたいです。
はい。
まず、いただいた台本をしっかり読み込むことから始めます。
そして、声優さんにクライアントさんのイメージに合うお芝居をしていただくためのお手伝い、とでも言いましょうか。
演技指導というとおこがましいですけど、収録現場の進行やディレクションを主に行っています。
台本を読み込む際は、キャラクターがどんな役なのかがわかる資料や、
物語の舞台・世界観がわかる資料、そしてシナリオを通しでいただきます。
ファンタジーなのかリアルな作風なのか、登場人物はアニメ調なのかリアル調なのか、どれくらいコミカルで、どれくらいシリアスなのか…
クライアントさんへのヒアリングで、そういった作品の雰囲気に対する認識を細かく調整していきます。
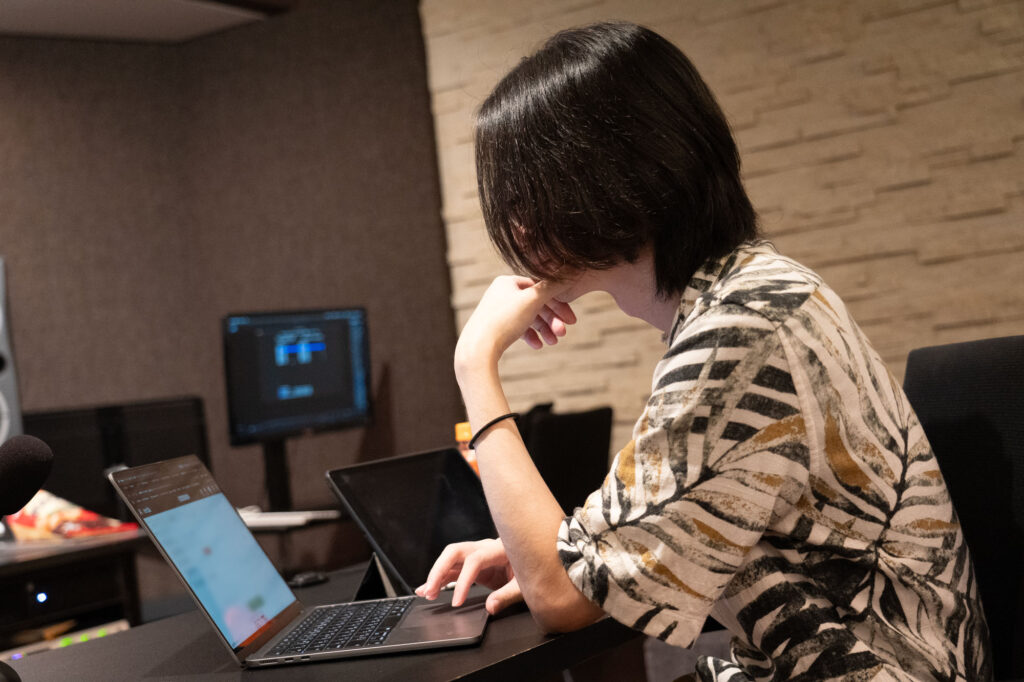
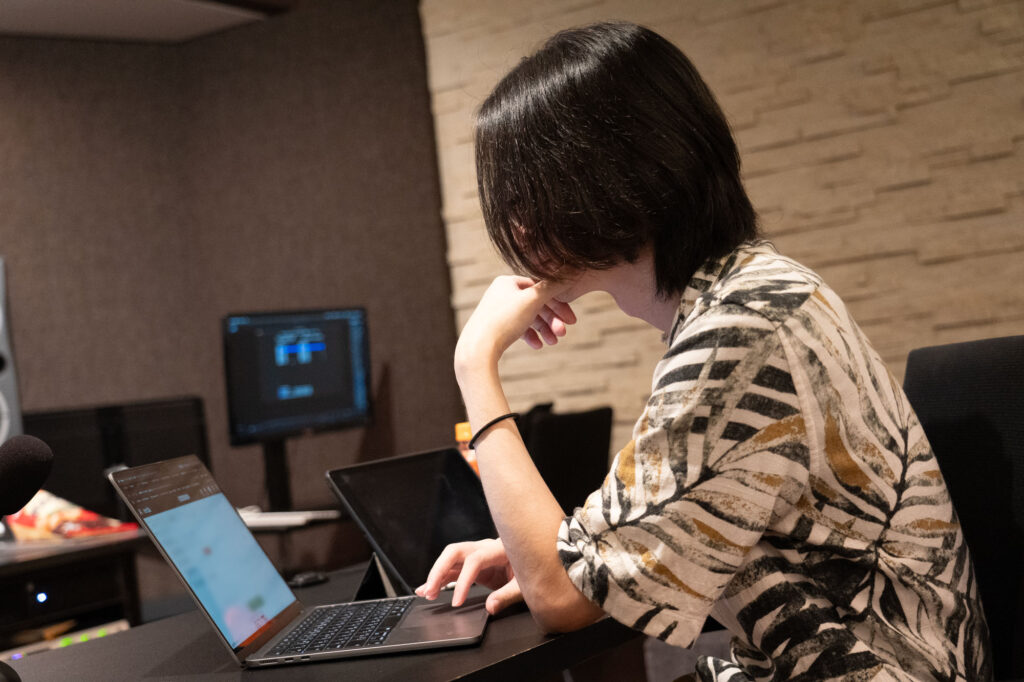
これらの資料やヒアリングした内容をもとに声優さんに演じていただいて、
そのシーンで伝えたい内容が、プレイヤーへより明確に伝わるようお芝居を調整します。
加えて、そのお芝居を聞いたクライアントさんが感じたこと、気になったことがあれば伺い、
すり合わせた内容を声優さん向けに変換してお伝えする。
こういった流れで収録現場でのお芝居を組み立てていく、という感じですね。
──なるほど。クライアントさんと声優さんの橋渡し的な存在といいますか。
そうですね。
クライアントさんの考える正解イメージに一番近い世界観を音声で表現するには、
声優さんのお芝居をアシストすることが欠かせないと考えています。
ゲーム全体のストーリーや画面上の演出、音楽など、プレイヤーにどう見せたいかでそのキャラクターのことを考えているクライアントさんと、
ゲームの中に生きるキャラクターの立場に立ってお芝居をする声優さんではキャラクターを捉える視点が違います。
「もっと強そうに演じてほしい」のようなざっくりとしたフィードバックをいただくこともあるんですが、
その指示ひとつとっても、クライアントさんの考える「強そう」と、声優さんの考える「強そう」が違う可能性がありますよね。


──確かに!場面やキャラクターによっては、自信満々に堂々としている方が強そうかもしれないし、静かに威圧している方が強そうかもしれない……認識を合わせないと全然違うアウトプットになりそうです。
そうなんです。
そのままお伝えしてしまうとお芝居が声優さん任せになってしまい、
「正解ではあるんだけど、なんかちょっと違うな」というズレが起こりやすくなってしまいます。
だからこそ、キャラクターがどのような感情をどういう理由で感じているのか、役としての感情をどういう方向に持っていってほしいのかを演出が補足して、
クライアントさんのイメージに近いお芝居を声優さんに演じてもらいやすくすることが必要なんです。
ゲームの音声収録特有の難しさと演出の役割
──クライアントさんのイメージに一番近い世界観を創り上げるうえで、課題となることはあるのでしょうか。
そうですね。
ゲームの音声収録は抜き録り、つまり1人1人収録していくのが基本なんですが…
この、かけ合い相手がいない、流れで芝居ができないことが、ゲームの収録では一番難しいところではないかと思います。
先程述べた、「演出が声優さんのお芝居をアシストすることが欠かせない」と私が考えているところにも繋がってきますね。


──話しかけた相手の反応がわからないまま進むということですね…?
そうなんです。
アニメーションの収録現場など、かけ合いで収録できる環境であれば、声優さん同士で芝居のテンション感や台詞のキャッチボールをできるんですが。
抜き撮りだと、演出からの情報がなければ「他のキャラクターがどう喋っているのか」「どのような声優さんが演じているのか」といった情報を得られないので、手探りで演じてもらうことになってしまいます。
この状況をそのままにしてしまうと、声優さんそれぞれの判断に任せることになってしまい、役ごと、収録日ごとのズレが発生してしまうんです。
そこで演出が「どういう作品で」「どういった場面で」「どれくらいの距離感で」「どんな雰囲気で」といったイメージを収録前にしっかり組み立ててお伝えしておくことで、
声優さんごとのお芝居に揺れが生じることなく、作品全体に統一感を持たせることができます。
「こういう想定で録っています」というのをお伝えできるよう事前に組み立てることが、スムーズな収録と高いクオリティに繋がりますね。
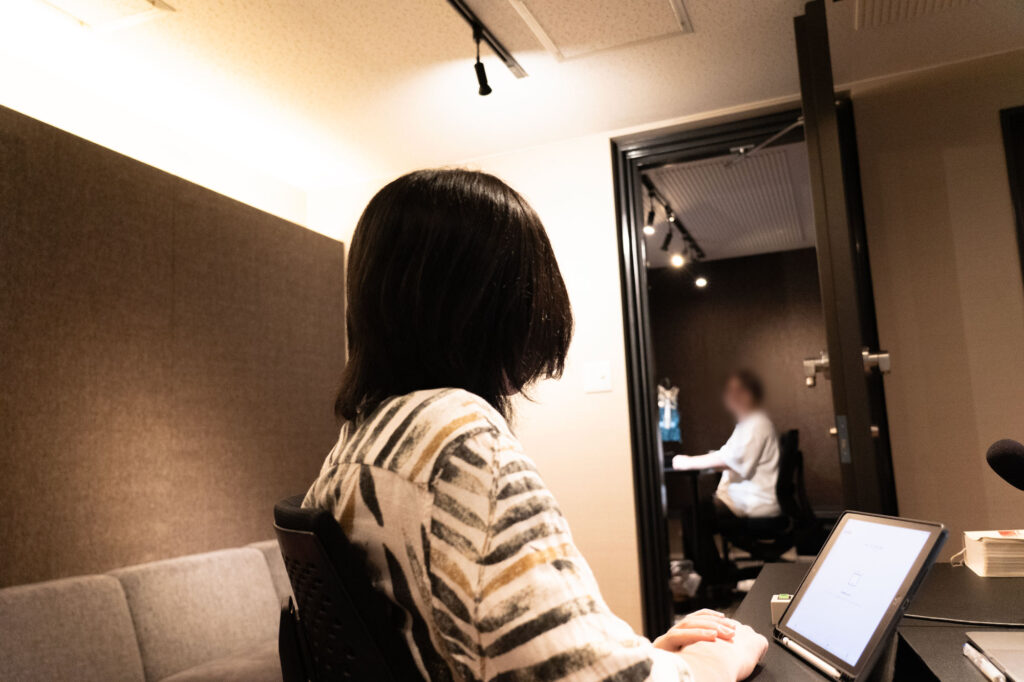
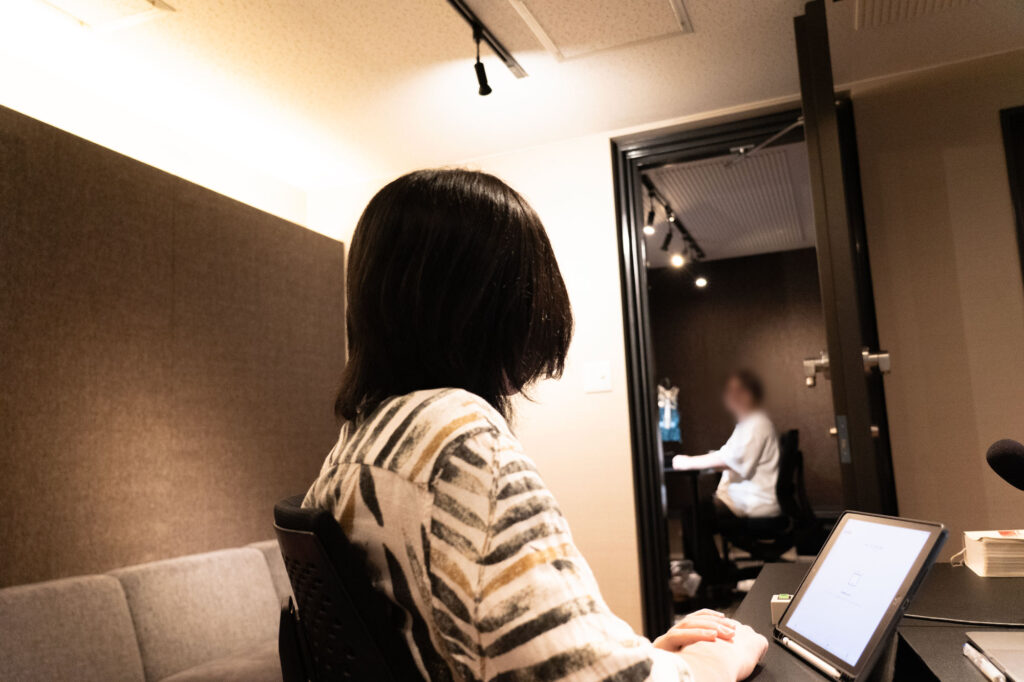
──抜き撮りでも統一感を持たせることが、難しくも大切なことなんですね。
おっしゃる通りです。
ゲーム収録ではもう一つ、収録時に画がないことも難しい点だと思います。
画があれば、どれくらい動いているか…たとえば戦闘のシーンなら「どのタイミングで動き出し、武器を振っているか」といった情報を得られますが、ゲームだと正解がないことが多いんです。
必殺技を放つようなシーンでのセリフも、「技のだいたい最後に言う」という大まかな目安はあっても、明確に決まっていないこともよくあります。
──開発中といいますか、世にまだ出てないからこそわからないことも多いと。
ええ。
抜き撮りであるために声優さんが得られる作品の情報が制限されているうえ、視覚的に得られる情報も少ない。
お芝居の方向性に対する不明瞭さを声優さんも抱えているはずで、不安を抱えたまま収録しても、きっとクライアントさんのイメージには近づかないと思います。
だからこそ、演出がその不明瞭さをしっかり解消して、最良の形を提示していく必要があると考えています。
ローカライズの関わるゲーム音声収録の難しさと演出の役割
──ジーアングルでは、海外ゲームのクライアントさんから日本語での収録についてご相談いただくことも増えていますよね。こういったローカライズについてはいかがですか?
特にAAAタイトルなどでは、シナリオ制作と音声収録が同時に進行していることが多いので、そこにも難しさを感じますね。
全6章のゲームだったとして、まずは1〜2章を先に収録することがよくあります。
その場合、「最終的にこのキャラクターがどう落ち着くのか」が、演出も声優さんもぼんやりとしかわからないケースが珍しくありません。
そういう場合は、原音となる英語の声優さんのお芝居に合わせながら収録することにはなるのですが、
そのお芝居が本当に正解なのか?という点も疑う必要があります。
たとえば汎用的な台詞…ダメージを負った時の声や、何かに押しつぶされる台詞がありますよね。
──ぐっ!とかですね。
そうです!
こういった台詞には「どういう時に流れますよ」といった注釈が書かれているのですが、
原音を聴いてみると「これは押しつぶされているように聞こえないな」と感じることもままありまして。
そんな時演出は、原音以外にも注釈や、その台詞の前後の台詞など、手がかりすべてを参考にしながら、
最終的にそのゲームに合うよう取捨選択して、着地点を探っていく必要があります。
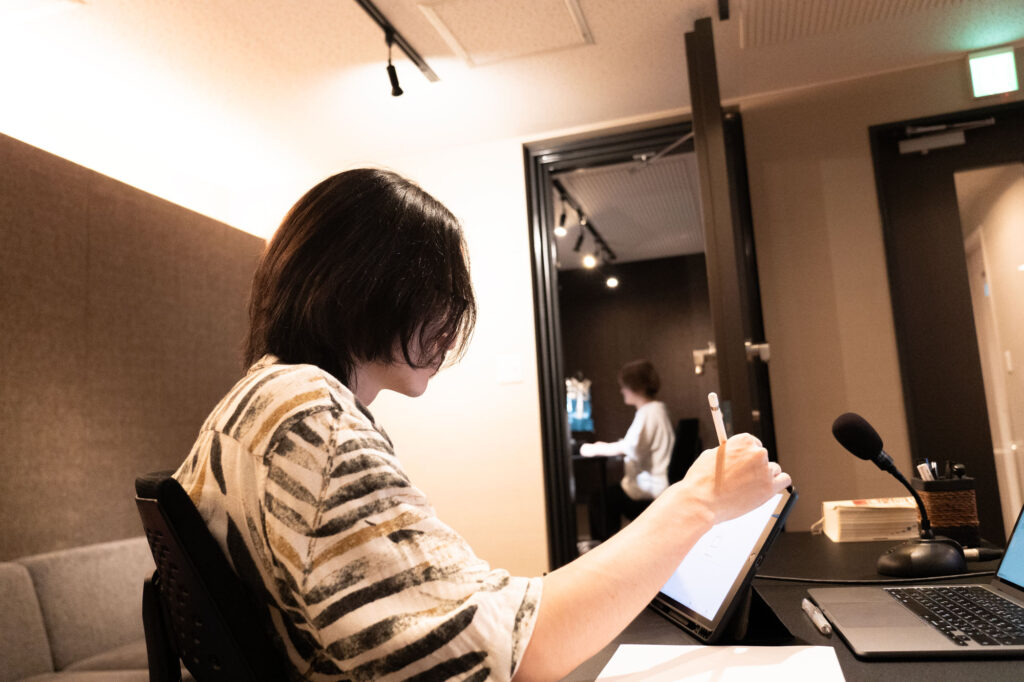
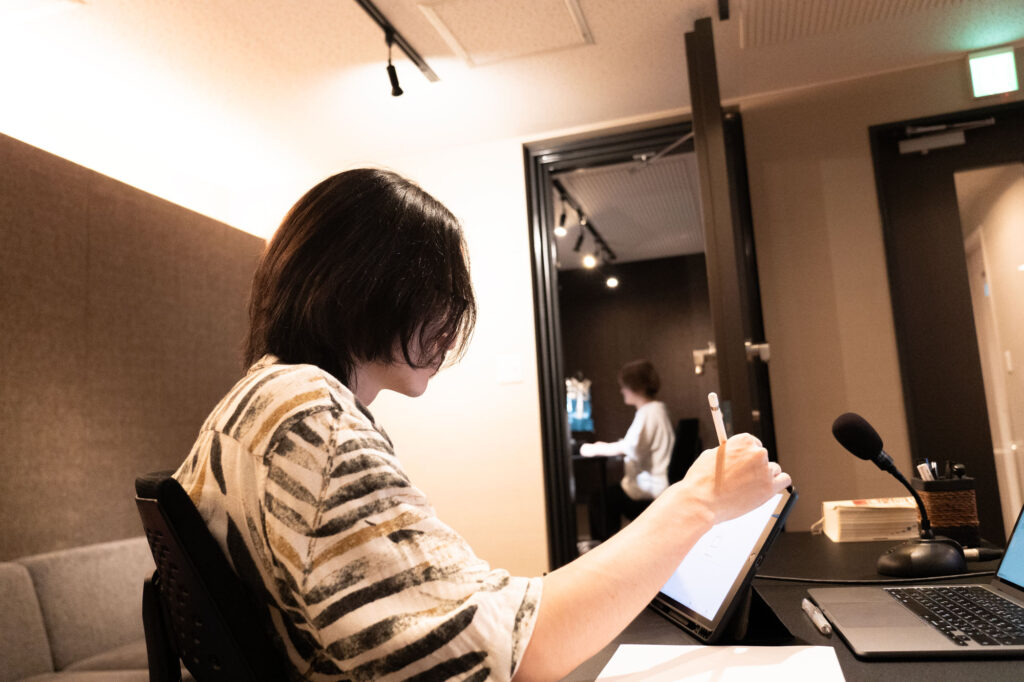
そして抜き録りというハードルも加わるので、かなり歯ごたえがありますね。
原音を頼りにしつつ、今わかっているストーリーから推理して録らないといけません。
全6章を聞いた時に整合性が取れるよう組み立てていくのは、演出の腕の見せ所だなと。
──なるほど。原音というと、元となる言語によって気を付けるべき内容が変わることはあるのでしょうか。
そうですね。
英→日ローカライズの場合、吹き替え的な言い回しは許容されやすいのですが、
アニメーションテイストが多い中国ゲームで吹き替え的な言い回しを使ってしまうと、すごく違和感が出てしまうことがあります。
中→日ローカライズでは、この「違和感」を出さないようにすることも大切なので、テキスト監修もよく行っていますね。
原神や鳴潮をイメージしてもらえるとわかりやすいと思うんですが、こういった中国ゲームは写実的なゲームとはまたちょっと違います。
日本育ちの高校生っぽいキャラクターが、友達に「Hiジェニー」って声をかけることはないじゃないですか(笑)


──たしかに!(笑) 洋画っぽいというか、アニメやゲームのキャラクターが喋っているようには聞こえない気がします。
そうなんです。
実際に僕が携わった「鈴蘭の剣」というゲームでは、当初クライアントさんからローカライズ作品としては悪くない翻訳クオリティの台本をいただいていたんですが、
キャラクターと紐づけて見た時にどうしても翻訳感が滲み出ていました。
そこで、クライアントさんと相談しながら口語的でキャラクターらしい言い回しに調整したり、
語尾や、関係性からくる口調の変化など、全体を通して世界観やそれぞれのキャラクターに寄り添った調整を行いました。
結果として日本プレイヤーの皆さんにも好評をいただくことができて、演出としてゲームのクオリティアップに貢献できた実感がありましたね。


https://www.g-angle.co.jp/works/10484/
そもそも日本語は語尾や喋り方、一人称だけでとんでもない種類がある難しい言語ですから、
声優さんから良いお芝居を頂くために、単純に間違っている日本語を直したり、口調を整えることも多いですね。
ゲームのテイスト、世界観に合う「このキャラクターだったらこう喋る」を、日本人が理解しやすいように、伝わりやすいように調整していくことが、ローカライズにおける演出の重要な役割だと思います。
ゲームの音声収録に演出が参画するメリット
──ここまで演出の役割について伺いましたが、ゲームの音声収録に演出が参画することでどのようなメリットがあるのでしょうか?
まず第一に、作品全体の統一感を担保できる点があります。
先程もお話しましたが、クライアントさん側と声優さん側では、同じキャラクターでも見ている視点が異なります。
クライアントさんは「ユーザー目線」で作品全体を見ていますし、声優さんは「そのキャラクターの目線」で役に向き合っています。
クライアントさんとしては「こう見せたい」という明確なイメージがあっても、それをどう伝えたら声優さんに伝わるのか分からない、という状況は少なくありません。
そこで演出家が入ることで「こうやってもらうのが一番いいですよ」とお伝えでき、最短距離で成果にたどり着けるんです。
──クライアントさんの意図を汲み取って、役者さんに伝わる言葉に「翻訳」するイメージに近いでしょうか。
「クライアントさんの解釈をまず自分自身が正確に汲み取った上で、それを声優さんに伝わる言い方で伝えないといけない」という意味では、確かに翻訳に近いかもしれませんね。


第二のメリットは、作品の臨場感や奥行きを演出できることです。
特に、メインストーリーが立ち絵で進むゲームのような、映像や視覚的な表現が限られるケースでは、その重要性が増します。
距離感やシチュエーション…「キャラクター同士が顔を見合わせているか、はたまたどちらかはそらしているか」など、
目に見えない動きの情報を役者さんに明確に伝えることで、奥行きのあるお芝居に繋がります。
場合によっては戦闘シーンが立ち絵と画面上のエフェクトだけで行われることもありますよね。
そういった時は音声に動きを乗せないと、何をしているかイメージしづらく、没入感も薄れてしまいます。
収録現場でかけ合いをできないからこそ、演出がその場でお芝居のアシストすることで、
役者さんの演技力だけに頼ることなく、クライアントさんのイメージする臨場感をしっかりと表現できるんです。
──立ち絵だけでストーリーが進んでいる時、そのシーンを理解するのに音や演技が頼りになりますもんね。
そうなんです。
ユーザーの体験をより豊かなものにするために、「このシーンはどう構成して演出していこうか」と収録中常に考えていますね。


そして第三のメリットとして、クライアントさんの理想をさらに上回る提案ができる、という点が挙げられます。
演出家は、クライアントさんの意見をそのまま役者さんに伝えるだけではいけないと考えています。
日本語としての正しさはもちろん、
演出として持っている「このシーンはこうした方が絶対に良くなる」というイメージを時にはクライアントさんに提案したうえで、声優さんに伝えることが大切ですね。
ただ、これは演出のひとりよがりになってはいけません。
クライアントさんと常に相談しながら、「こう見せたいんだったら、こんな感じにしませんか?」といった対話を重ねていくことで、
表現に限界がある場合でも、キャラクターが際立つように工夫できます。
演出への向き合い方
──最後に、プロの演出として、日頃から大切にしているマインドや心がけがあれば教えていただけますか?
ゲームの演出は、極論を言えば「名乗ったもん勝ち」だと思っています。
クライアントさんから「ここはもっと強く演じてほしい」というざっくりとしたディレクションがあったとして、
その指示をそのまま役者さんに伝えて、それでOKが出れば、一見仕事は成立してしまうからです。
ただ、そうやってできたコンテンツは、どこかあっさりしていたり、違和感があったり、臨場感がなかったりするんです。


──表面的な業務だけでは、本当に良いゲーム音声にならないということですね。
はい。
クライアントさんと一緒に音声面から世界観を創り上げるのが演出の役割ですから。
先程もお話したように、演出は自分のイメージを押し付けるだけでも、クライアントさんの意見をそのまま伝えるだけでもいけません。
だからこそ、僕は演出という役割を担ううえで「クライアントさん以上にその作品を好きになる」ことを一番大切にしています。
クライアントさんとその作品について深く語り合えるほどモチベーションを高く保っていれば、手を抜くなんて考えられませんからね。
ジーアングルの演出として作品に入るからには、ジーアングルクオリティの作品にしなくてはいけないと思っています。
もし「ここをもう少し頑張れば100点になるのに」という部分があれば、絶対に妥協したくない。
クライアントさん以上にその作品を好きになることで、クライアントさんにも「この人、本当にこの作品を大切にしてくれているな」と感じていただけますし、信頼関係も生まれて、より深い相談をしてもらいやすくなると思います。
ジーアングルが演出に携わった実績のご紹介
佐藤滉世が携わった実績の一部をご紹介します。
鈴蘭の剣


声優キャスティング及び音声収録、インタビュー撮影を担当いたしました。
新月同行


日本語音声、ボイス実装部分の声優キャスティングおよび音声収録、インタビュー動画の声優キャスティングおよび撮影を担当いたしました。
逆転オセロニア


声優キャスティング及び音声収録を担当いたしました。
マルコと銀河竜
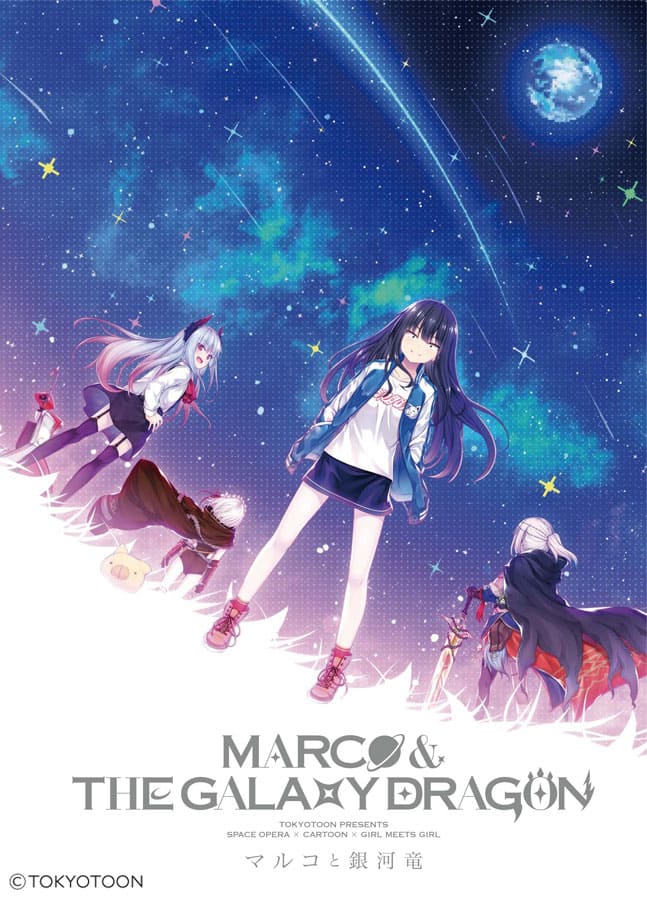
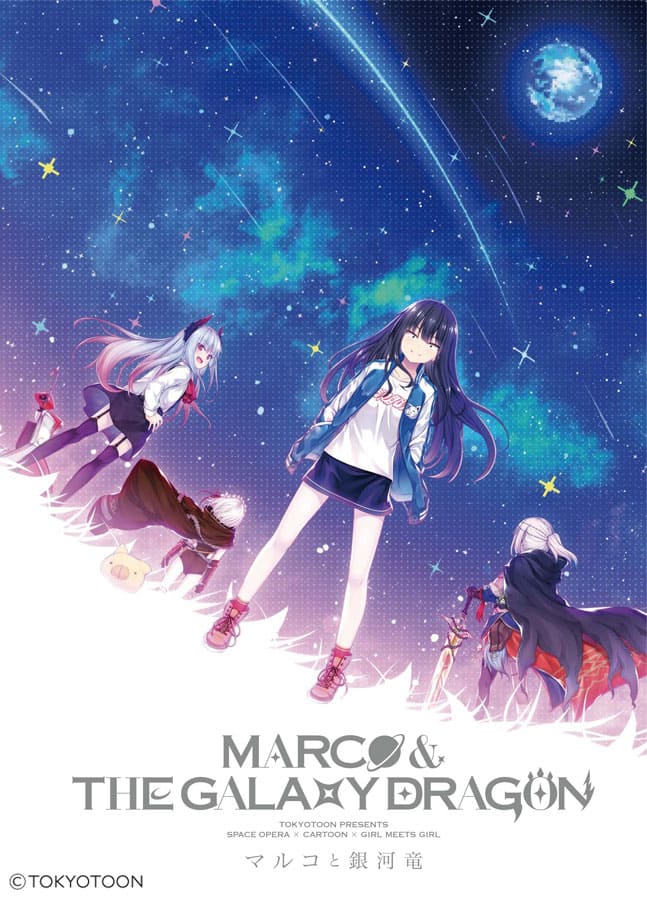
声優キャスティング及び音声収録を担当いたしました。
ゲーム音声収録はジーアングルまで!


ゲームの音声収録における演出家の役割やメリットなどをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
コンシューマーゲーム、PCゲームやスマホアプリゲームなど、日夜生まれるゲーム作品に欠かせない要素である音声。
声優さんの人気も後押しし、「キャラクターの声」への注目度は日々増しています。
ジーアングルでは、声優キャスティングから収録まで、ゲーム音声制作をワンストップでサポートいたします。
ゲームにおける声優収録は、抜き録りならではの難しさがありますが、
クオリティを第一に妥協せず、最短距離でスムーズな収録進行をできるよう努めています。
ゲームの音声収録にお困りの方や、音声面からゲームの世界観を深めたい方は、ぜひジーアングルにご相談ください!
ジーアングルでは正社員/業務委託を対象に、演出家(音響監督/ボイスディレクター)を募集中です。
ジーアングルの演出のお仕事に少しでも興味をお持ちいただけましたら、ぜひ採用ページをご覧ください。









